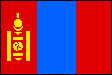
Mongolia
ウランバートル逍遥(前編)
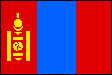
Mongolia
ウランバートル逍遥(前編)
スヘバートル像 モンゴル国 |
|
この夏(註 平成13年)、ひょんな経緯からモンゴルを訪れることになった。モンゴルとは、申すまでもなく、アジア地図の天辺に横たわる草原の国だ。そこでは昔ながらの民族衣装に身を包んだ遊牧民が、ゲルと呼ばれる丸いテントに住み、先進国と呼ばれる国々の時間の概念と大きくかけ離れた生活を営んでいる。私にとってはブータンや北朝鮮とともにアジアの白地図に残されている数少ない未踏国のひとつだった。しかし、殖やしすぎた家畜と異常な寒波がもたらした雪害の報道もまだ記憶に新しく、おまけに今年のNHKは、永田町や霞ヶ関の啓蒙を試みるかのように、大河ドラマのテーマに元寇を取り上げている。関西新空港から首都・ウランバートルまでの飛行時間はほぼ4時間。バンコクよりも幾らか近い。 |
ウランバートル
|
深夜の空港から市中へ向かう真っ暗闇の一本道で、いきなり路肩にぼんやり浮かび上がった白いゲルを見た。 |
| ウランバートルのオペラ座 |
| |
|
髪を金色に染めた若者の群れが歩道を闊歩していく。
|
|
東南アジアでは、よくもわるくも日本が一番目立つ国で、韓国は金満北東アジアの”おまけ国家”に位置付けられている。インドシナ半島の農村やブルーカラーの無知な連中の中には、威張り散らす韓国人へのうらみつらみを、お人好しの日本人に叩きつけて来るやつも少なからずいるものだ。ところがモンゴル人の東方観は、様相が異なる。モンゴル人にとって、最も身近な東アジアの国は韓国で、日本はその背後に控える韓国経済の保障人といった、あくまでも二次的な国家に据え置かれているらしい。街を見回してみると、なるほど韓国との経済的、文化的な結びつきがすぐわかる。老朽化が甚だしいソ連製のワゴン車・ウアズィは、車道の主役の座を、現代のエクセラに譲り渡しつつある。短い夏を謳歌する若い女性のファッションは明洞モード一色に塗りつぶされ、化粧のパターンも鐘路一街を闊歩している手合いと大差がない。流れるモンゴリアンポップスだって、ハングルの歌詞に挿し替えても違和感のない旋律である。目抜き通りの垢抜けたカフェも、アメリカかぶれが韓国流だった。おまけに、逗留するホテルのそばには、SEOUL
STREETという名称の道路まである。 |
| 町で最大のデパート前には韓国車が展示されていた |
| 郊外へ・・・ |
|
今回のモンゴル行きは、鉱山を視察する業務が主目的だった。山へ案内してくれたのは、ツベリンさんという、日本語が達者な60年配のおやじさんだった。ツベリンさんは子供の頃、日本人抑留者から日本語の手ほどきをうけ、爾来、非凡な日本贔屓で社会主義モンゴルを生き抜いてきたという。そのくせ”元KGBの工作員”と噂されていたりして、よくわけのわからない御仁だった。ホテルのロビーで会うと、開口一番、バスの車中で携帯電話を掏りに盗られた、と嘆いていたほどだから、KGBにしてはいまひとつ頼りなかった。 |
|
首都近郊の草原 |